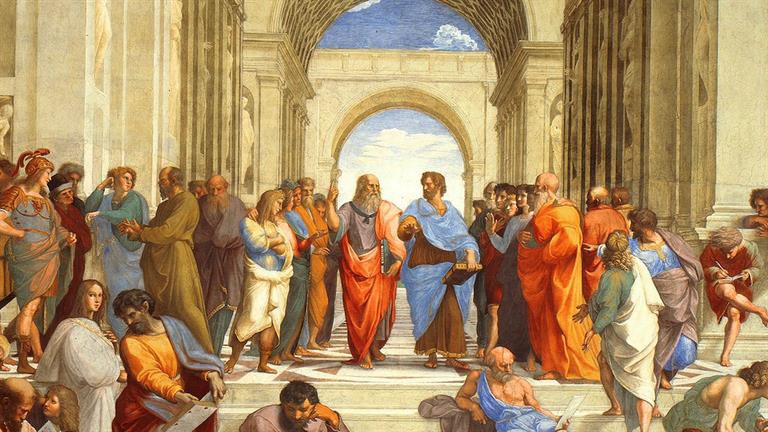朝、机に向かった瞬間から「何から手をつけるべきか」が決められず10分が消えた。ToDoリストを開くと、重要なタスクも、いつかやりたい願望も、不安も全部混ざっている。それが嫌でSNSを開く。焦りが増して閉じる。また何をするべきかわからなくなり時間が溶ける。「今日も何も進まなかった」が積み重なっていく。
自分が問題だと思っているものを書き出して分類してみたら、それは解決すべき課題ではなくて、ただの願望だったり、不安だったり、漠然としていてゴールが決まっていないものばかりだった。これらは問題のようであって、考えたところで解決もしないし、次のアクションも決まらないノイズだった。
問題を正しく見極めて行動だけにフォーカスすることで、手を動かせるようになり、逆に考えてもしかたないことをオフロードしやすくなった。
雑念による苦しみ
自分の頭の中にあったものの多くは、「未定義の願望」と「処理しない不安」だった。蓋を開けてみればそれらはタスクですらなかったし、次のようなことが起こった
- 「もっとできる自分を見せなきゃ」と焦って何かを証明したいだけの願望がリソースを占拠
- このままでいいのか?と将来の不安に飲まれ、漠然とした不安をタスク扱いして混乱
- 何者になりたいかといった終わりのない問いをタスクとしてしまって破綻
- 現実と期待の距離が処理されないまま、成果が出ても満足できず常に足りない感覚が残る
こうした状況になると、解決しない問題が頭の中に残り続けて考えるのが嫌になっていた。現実を見ないためにSNSを見たり広告アプリをやったり…。さらにパフォーマンスを落とすようなループに陥っていた。
悪循環から抜け出すためのプロセス
自分はタスク管理やGTDについて興味があったから、それらを使えば解決できるはずだった。知識はあるのに有効活用できていなかった。自分のやり方を見直して何がダメだったのかを考えることにした。ここからはプロセスと自分の気づきを紹介する
まずはとにかく書き出す
紙またはホワイトボードを使って頭に思い浮かぶことをすべて書く。
自分は「考えてから書く」癖があって、それがずっと悪循環を作っていた。綺麗にまとめようとすると、結局考えている風で止まる。判断を避けるための言い訳として、形式や書き方にこだわっていた。
だから、思いついたものを全部、荒く、汚く、即書くことにした。文章でも単語でも、言いかけてもいい。「やらなきゃ」「気になる」「怖い」「面倒くさい」すらそのまま書く。書ければ勝ちで、意味が通っていなくても構わない。
紙かホワイトボードを使ったのは、後で捨てられるからだ。デジタルだと保存前提になってしまい、「残す価値があるかどうか」を気にして手が止まる。紙ならどうせゴミになると思えば遠慮なく出せる。雑念はまだ消えないが、ここでの目的は思考を止めて、手を動かす側に自分を強制的に引き戻すことだった。
とにかく書き散らす。意味付けや整理は次の段階でやると決めて、ひたすら吐き出す。この吐き出すだけの時間を設けたことで、ようやくスタートラインに立てた。
行動、プロジェクト、ノイズ
次にやったのは、書き出したものを無差別に扱うのをやめることだった。自分はこれまで、締め切りのあるタスクも、“いつかすごい人になりたい”みたいな抽象的な願望も、将来の漠然とした不安も、全部同じテーブルに置いていた。その時点で勝負にならない。扱う性質が違うものを同列に並べれば、そりゃ頭はパンクする。
だから、強制的に三つに分けた。
- 行動(A):30分以内で終わる、完了が具体的に定義できるもの
- プロジェクト(P):複数の行動に分解できるまとまり
- ノイズ(N):願望、不安、自己評価、未定義のモヤモヤ
ここで重要なのは、“行動”と名付けた以上、その場で終わらせられる状態にまで削ぎ落とすこと。曖昧な表現のまま「行動扱い」すると、また迷うだけになる。表現が曖昧なら書き直す。
プロジェクトについても同じで、完了条件を言語化できないものは、まだプロジェクトですらない。ただの妄想か願望だ。手をつける価値がない。
この分類をした瞬間、自分が抱えていた“問題のように見える塊”の大半がノイズだったことが露骨にわかった。行動にもプロジェクトにも落とせないものは、忘れるか、定義し直さない限り永遠に自分を消耗させ続ける負債だった。
このステップでようやく、自分が戦うべき相手と、捨てるべき雑音が切り分けられた。
ノイズを忘れる
ノイズに書いたものは書いた時点で忘れることにする。
プロジェクトの分割
プロジェクトには適切な名前をつけた。「京都のイベント」とか「睡眠改善」とかだ。
次に目的を明確にする。ここで理想や期待を混同しすぎないようにした。例えば京都のイベントプロジェクトの場合の目的は、
- イベントに参加する
- 交通・宿泊の手配を完了して、当日焦らない状態にする
- 予算を5万円以内にする
と書いた。ここが書けない場合はそのプロジェクトには着手しないことにした。また、目的には感情や理想は入れないようにした。これらは自分で制御できることではないからノイズとして扱う。
次はプロジェクトの要素をリストアップする。
#### 必要なもの - 交通手段(往復) - 必要時間(会場到着〜撤収) - 宿泊 - 持ち物 - イベントのチケット #### 現実の制約 - 入場時間 - 交通の接続(終電、バスの本数) - 予算・休みの取得 #### 複数回行う必要があるもの - チケット販売情報のチェック - 出発前のチェックリスト確認 #### 一度やれば済むもの - チケット確保 - 宿の予約 - 行き方の決定
ここまでできたら次は観測可能な行動に変換していく。このときのルールとして「誰が見てもやったと判断できる」ことを基準にした。ぼんやりと「余裕を持って行く」とか「移動の準備をする」みたいには書かない。
行動する
行動に分類したものは時間を決めて完了させる。もし、行動に移せない理由があるならそれを解決するための行動を作る
トリガーリストを作る
頭に思い浮かんだもの以外にも対応しなければならないことはある。重要な手続きを忘れていないか?忘れている連絡はないか?未整理のままになっているものはないか?取りこぼしがないように、自分が気にしておくべきものはトリガーリストとして、あらかじめ用意しておこう。
何で管理するか
はじめの書き出しは紙で行うのが良いと思っている。殴り書いていいし、レイアウトも必要ないし、図も書ける。
プロジェクトを管理したり階層構造、ラベルづけなどで分けたい場合はデジタルが向いている。ただしノイズを乗ると一気に管理するものが増えてしまうので、アナログで書いてデジタルに移すときにノイズを消せるといいと感じた。
まとめ
最終的にGTDのような形式になった。