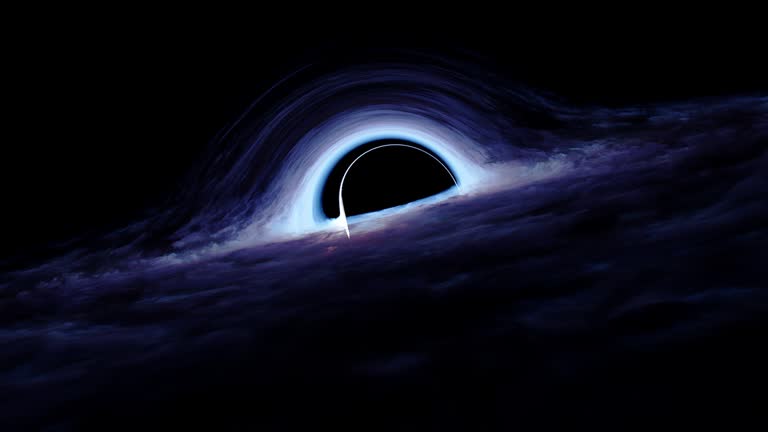アリストテレスの自然観
紀元前400年頃、古代ギリシア人のアリストテレスは、手に持った石が自然に落下することについて、「石を構成する土元素が本来の位置である地面に戻ろうとしている」と解釈した。そして、土元素が多いほど物体は重く、速く落ちると考えていた。
この考えは、以降中世まで信じられていた。人間が家に帰るように、動物が巣に帰るように、すべてのものは「本来の位置」に戻ろうとする性質があると考えられていた。これは生き物に限らず、火は天に本来の位置があるため上に昇ると考えられた。
一方で、天体はこの考え方で説明できなかった。天体は本来の位置を持たず、ずっと同じ動きをするように見えていたからだ。これについては、「地上の存在と天上の存在は本質的に異なっているため、地上の法則は天体には適用されない」と考えられた。
ガリレオの落体実験
中世以降になるとアリストテレスの考え方に疑問が投げかけられるようになった。実験によって異なる重さの物体も同時に地面に到達することなどがわかっていた。
その頃、ガリレオ・ガリレイは物体の落下速度がどのようにして決まるのかを考えていた。物体の性質によるのか、落下距離によるのか、落下時間によるのかを調べていた。最終的に物体の落下速度は「落下時間にのみ依存する」という仮説を立てた。
また、斜面に球を転がす実験を行い、物体は外から力が加わらない限りは等速直線運動をすることも明らかにした。これは現代の慣性の法則に近いものであった。
しかし、ガリレオの実験をもってしても天体の動きを説明することはできず、この法則もまた地上の存在と天上の存在を同じように扱うことはできなかった。
ケプラーの法則
「神は完全な運動を造る」という思想に基づいて、天体の動きは完全な円運動をすると考えられていた。しかし、天体はまれに逆行するような動きをすることも知られていた。自然学者たちは、天体は小さな円運動をしながらある天体の周りを大きく円運動しているとしてこの現象を説明した。
ティコ・ブラーエは、太陽中心説を信じており、その動きを説明するために惑星の天体運動を観測していた。ティコによる分析はそれまでよりもずっと精度が高かった。ヨハネス・ケプラーは、この観測データを元に太陽と火星の動きを定式化することを試みていたが、円運動を仮定すると観測データとズレがあることに気づいた。これまでの円運動説をやめ、楕円軌道を仮定するとうまくいくことに気づいた(ケプラーの第1法則)。
続けて、惑星の近くでは速度が大きく離れた場所では速度が小さくなること(ケプラーの第2法則)、惑星の公転周期は楕円軌道の長半径にのみ依存すること(ケプラーの第3法則)なども明らかにした。
ニュートンの万有引力
ケプラーの発見によって惑星運動はうまく説明できることがわかったが、なぜそうなるのかはわかっていなかった。ガリレオが発見したように、慣性の法則によって物体は力が加わらなければ直線運動をするはずだった。逆に言えば、直線ではなく楕円運動をするのなら太陽方向に力が働いているということになる。
1666年頃、ロバート・フックは引力についての講演を行った。フックは「天体間にも引力が作用していること」「引力によって天体は楕円軌道を描くこと」「天体同士が近いほど引力が大きいこと」などを述べた(ただし引力と距離の関係については明らかにされていない)。
フックは自分の学説について、ニュートンに意見を求めた。ニュートンは、地球の引力が月まで影響を及ぼしているとした場合の計算をやり直すことにした。月が直線運動をした場合の位置から実際に観測されている位置まで地球の引力によって「落下している」と想定した。計算したところ、月の位置での地球方向への加速度が地球地表面にける重力加速度の3600分の1であることがわかった。地球と月までの距離が地球の半径の60倍に相当することから「引力は距離の2乗に反比例する」ことを発見した。
物体の落下時の力は地球の地表面では
\[F = mg
\]
で表された。ニュートンは、この重力加速度も地表までの距離(=地球の半径)の逆二乗に比例していて、同様の力が月と地球の間にも働いている、さらには他の惑星を含めすべての物質にはこの引力が働いていると示した。
\[F = G \frac{m_1m_2}{R^2}
\]
万有引力の公式を使った演習問題
地球表面の重力加速度を万有引力から導く
地球の質量を \(M\)、半径を \(R\)、地表にある物体の質量を \(m\) とする。
地表で物体に働く万有引力は
\[
F = G \frac{M m}{R^2}
\]
である。
他方、運動方程式より
\[F = m a
\]
が成り立つ。
両式を等置し、質量 \(m\) を消去すると
\[m a = G \frac{M m}{R^2}
\quad\Rightarrow\quad
a = \frac{G M}{R^2}.
\]
したがって、地表での重力加速度は
\[g = \frac{GM}{R^2}.
\]
地心距離を \(2R\) とした場合の円軌道の速度
地球の質量を \(M\)、第一宇宙速度を
\[v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}}
\]
とする。
半径 \(2R\) の円軌道で衛星(質量 \(m\))に働く向心力は
\[\frac{m v_2^2}{2R}.
\]
同時に、衛星に働く万有引力は
\[F = G \frac{M m}{(2R)^2}
= G \frac{M m}{4 R^2}.
\]
向心力=重力より
\[\frac{v_2^2}{2R}
= \frac{GM}{4R^2}.
\]
両辺に \(2R\) を掛けて整理すると
\[v_2^2 = \frac{GM}{2R},
\qquad
v_2 = \sqrt{\frac{GM}{2R}}.
\]
したがって
\[
v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} v_1.
\]
地球と月の重力が釣り合う点の位置
地球の質量を \(M_E\)、月の質量を \(M_M\)、地球と月の距離を \(D\) とする。
地球側から距離 \(x\) の点において重力が釣り合う条件は
\frac{G M_E}{x^2}
=
\frac{G M_M}{(D – x)^2}.
\]
\(G\) を消し、平方根を取ると
\[\frac{\sqrt{M_E}}{x}
=
\frac{\sqrt{M_M}}{D – x}.
\]
両辺を入れ替えて比の形にすると
\[\frac{D – x}{x}
=
\sqrt{\frac{M_M}{M_E}}.
\]
これを \(x\) について解くと
\[\frac{D}{x}
=
1 + \sqrt{\frac{M_M}{M_E}},
\] \[
x
=
\frac{D}{1 + \sqrt{M_M/M_E}}.
\]
これが地球側から測った重力平衡点の位置である。