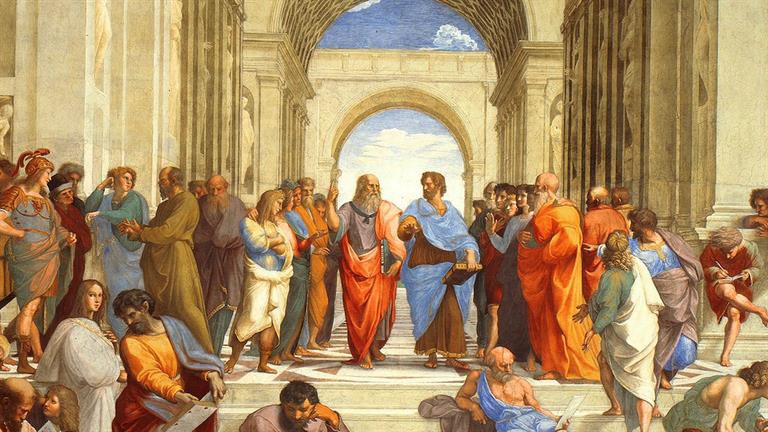会社に勤めていると生産性向上を目指したり強いられたりする。同じ取り組みを私生活でやろうとすると似ているけど少し勝手が違う。それに、こういったものを体系的に教えてくれるものは案外なくて、自分で勉強するしかない。自分なりに調べたりしたものをここでまとめることにした。
- 目標・方向性
- 計画・タスク管理
- リソース管理
- 環境設計
- プロセス改善・ふりかえり
- 思考・行動習慣
- 情報管理
目標・方向性
生産性の出発点は「どこへ向かうのか」を明確にすること。ビジョンやミッションを定め、長期・中期・短期の目標に落とし込む。OKRやSMARTを活用し、重要度と緊急度を見極めて優先順位をつけることで、エネルギーの投資先がはっきりする。
- ビジョンやミッションの明確化
- 長期・中期・短期の目標設定
- 優先順位づけ
ビジョンやミッションの明確化
生産性は単なる効率化ではなく、進むべき方向が明確であるほど意味を持つ。ビジョンやミッションを定義することで、行動が自分の価値観や目的に直結し、日々の選択に迷いが減る。
ほとんどの企業がビジョンを公開しているから調べてみるのも良い。でも、一般人が私生活で同じ事をするとなるとかなり抽象的で取り掛かりにくい。良い問いがあればいいと思うのだが、パッと思いつくのは『7つの習慣』で取り上げられている「お墓になんて書かれたいか?」だ。これは終わりを意識したものだけど、「どうなっていればうまくいっている状態か?」も良いヒントになる。
もし分かりにくければロールモデルを探してみる。「ああいう風になりたい!」と思う人物を思い浮かべて、どういうポイントを良いと思うのか言語化してみよう。フィクションの人物でも良いと思う。
言語化が難しければビジョンボードという手もある。なりたい自分や環境を表すような写真をとにかく1枚のボードに集める。こうすることで言葉にできなくてもそのボードを見れば自分の目指したい方向性を意識できるようになっていればいい。
このレベルの目標設定は、はじめに時間をかけた後で一年や半年単位で見直す。
長期・中期・短期の目標設定
大きな夢を持つだけでは日々の行動に結びつかない。測定可能な(達成できたかどうか明確に判断できるような)目標に落とし込み、逆算思考でステップを設計することで、理想が現実的な計画へと変わる。
おそらくビジョンは多面的だろうから、その中に複数のプロジェクトがあるはずだ。それぞれについて目標設定が必要になるだろう。長期・中期・短期とは書いたがどれくらいの期間に設定するかは自由で良いと思っている。10年先のことを具体的にイメージするのは難しいから、はじめは1年を長期と捉えても良いかもしれない。定期的な見直しを経て具体的で長期的な目標設定を目指そう。測定可能な目標にするにはOKR、SMARTといった手法がある。
優先順位づけ(アイゼンハワー・マトリクスなど)
やるべきことは無限にあるが、すべてに取り組む必要はない。重要度と緊急度を見極めることで、本当に価値あるタスクを優先できる。マトリクスを使えば判断基準が明確になる。
アイゼンハワー・マトリクスは米大統領アイゼンハワーが提唱した概念。重要性と緊急性によってタスクを分類する、『緊急ではないが重要』なタスクを増やすのが良いとされる。アイゼンハワー・マトリクスは複数の名著でも参照されていて、『7つの習慣』や『イシューからはじめよ』にも登場する。
計画
やるべきことを漠然と抱えるのではなく、具体的に分解して構造化することが鍵。WBSやマインドマップで全体像を描き、GTDやカンバンなどの仕組みに落とし込む。スケジューリングによって「いつやるか」を決めると、実行の精度が一気に高まる。
- タスク分解、構造化(WBS、マインドマップ)
- タスク管理システム(GTD、カンバン、To-doリスト)
- スケジューリング(カレンダー、タイムブロッキング)
タスク分解・構造化(WBS、マインドマップ)
大きなプロジェクトも細かく分解すれば取り組みやすくなる。WBSやマインドマップを使えば、全体像を把握しつつ一つひとつの行動に落とし込める。
プロジェクトか、ルーティンか
先に立てた目標を達成するまでにいくつかのタスクをこなす必要があるだろう。それは複数のタスクを順番に完了させて達成するものもあれば、継続的に何かを続けるようなものもある。前者をプロジェクトとして後者はルーティンと呼ぶ。この2つは性質が異なるので計画に落とし込むときにも別のものとして扱ったほうがうまくいく。
プロジェクトの性質を持つタスクはGTDを使って次にやることを明確にして進めていくのがよい。ルーティンに関しては複数のものを組み合わせたほうがうまくいく。カレンダーで枠だけを確保してまとめて処理するのをおすすめする。
タスク管理システム(GTD、カンバン、ToDoリスト)
タスクは頭で覚えておくのではなく、外部に預けることが重要。GTDで収集し、カンバンで流れを可視化し、シンプルなToDoリストで日々を進めることで、脳のリソースを解放できる。
タスクのアイデアやプロジェクトを収集するには GTD (Getting Things Done) のシステムが良い。やらなければいけないこと、考慮しないといけないことの全てを管理してくれる。David Allen の著書で詳しく知ることができるが、はじめての場合は次のガイドがおすすめだ。
スケジューリング(カレンダー、タイムブロッキング)
「いつやるか」を決めなければ、タスクは実行に移らない。カレンダーを活用して時間をブロックし、行動に適した枠を与えることで、計画が現実に変わる。
リストからピックアップしたものをカレンダーに入れてしまおう。予定はあとで変更してもかまわない。先に時間を確保して、その時間は決めたタスク以外のことを忘れるのが重要だ。どの時間にどんなタスクをやるのがいいかは普段の自分の調子を振り返って決める。午前に集中しやすいならその時間に重いタスクを割り当てて完了させてしまう。
リソース管理
時間は有限であり、集中力も消耗する資源。ポモドーロのようにリズムを設計し、朝の立ち上がりや夜の振り返りで一日の流れを整える。睡眠・運動・食事といった体調管理が土台になり、持続的なパフォーマンスを支える。
- ポモドーロテクニック
- 体調管理によるパフォーマンス維持
ポモドーロ、集中と休憩のリズム設計
長時間の作業は集中力を削る。ポモドーロのように集中と休憩のサイクルを設けることで、効率を保ちながら持続的に作業できる。
朝のルーティン、夜の振り返り
一日の始まりと終わりに儀式を持つことで、行動にリズムが生まれる。朝のルーティンでエンジンをかけ、夜の振り返りで修正点を見出すと翌日の質が高まる。
体調管理(睡眠・運動・食事)によるパフォーマンス維持
集中力や判断力は体調と直結している。睡眠の質を上げ、運動で血流を促し、食事でエネルギーを補うことが、最も根本的な生産性向上につながる。
環境設計
人は環境に大きく左右される。整ったデスクや最適化されたツール配置は、思考の余計な負荷を減らす。デジタル環境では通知制御やテンプレート化が効果的。集中を奪う要因を排除することで、本当に重要なことに没頭できる。
- 物理的環境(デスクまわり、配置など)
- デジタル環境(アプリや通知の最適化、テンプレート化)
- 阻害要因の排除(ノイズ、SNSなど)
物理的環境(デスクの整理、ツール配置)
散らかった環境は思考を乱す。デスクやツールの配置を整えれば、行動のハードルが下がり、余計なストレスを減らせる。
デジタル環境(アプリや通知の最適化、テンプレート化)
デジタルの雑音は想像以上に集中を奪う。通知を管理し、よく使う作業をテンプレート化すれば、作業効率が自然と上がる。
集中を阻害する要因の排除(ノイズキャンセリング、SNS制限)
最大の敵は誘惑やノイズ。ノイズキャンセリングやSNS制限を導入し、集中の質を守ることで本来の力を発揮できる。
プロセス改善
一度決めたやり方に固執せず、定期的にレビューすることで改善点が見えてくる。フィードバックを取り入れ、業務プロセスを自動化や効率化で磨き上げる。積み重ねが、再現性のある生産性を生み出す。
- 定期的なレビュー(週次、月次)
- フィードバック収集と改善
- プロセスの自動化、効率化
定期的にレビュー、ふりかえりをする
走り続けるだけでは改善は起きない。日次や週次、月次で棚卸しを行うことで、進捗や課題を冷静に見直せる。
まずレビューの対象は、プロジェクトやタスクそのものと、プロジェクトの進め方がどうだったかの2軸がある。後者はスクラムにおいてレトロスペクティブとも呼ばれるものだ。
また、ふりかえりにもいくつか方法がある。KPTやFun/Done/Learnなどだ。自分が大事だと思うのは、事実と感情を分けてふりかえること。どの方法にしても良い問いを事前に決めておくとふりかえりがしやすいと思う。いくつかの例を元に自分にあった問いかけをリストにすると良いだろう。
参考:
フィードバックの収集と改善
自分だけの視点に偏ると盲点が増える。フィードバックを積極的に取り入れ、改善を重ねることで作業プロセスは磨かれていく。
業務プロセスの自動化・効率化(ショートカット、スクリプト化)
手作業に時間を奪われるのは非効率。ショートカットやスクリプトを導入し、反復的な業務を自動化すれば、より価値の高い活動に集中できる。
思考・行動習慣
生産性は一時的な工夫ではなく、日々の習慣に支えられる。瞑想やマインドフルネスで集中力を鍛え、決断疲れを減らすために仕組みをシンプルにする。小さな行動を繰り返し、習慣化することで持続可能な成長が実現する。
- 集中力のトレーニング(瞑想、マインドフルネス)
- 決断疲れを減らす仕組み
- 習慣化
集中力のトレーニング(瞑想、マインドフルネス)
集中は天性のものではなく、鍛えられるスキル。瞑想やマインドフルネスによって注意力を制御し、必要な時に力を発揮できる状態を作る。
決断疲れを減らす仕組み(選択肢を減らす、標準化)
選択肢が多いほど意志力は消耗する。服装や食事を標準化するように、日常の選択を減らせば、本当に重要な決断に集中できる。

習慣化(小さな行動を積み上げる、習慣ループ設計)
一度の努力では成果は続かない。小さな行動を繰り返し、報酬と結びつけることで習慣ループが形成され、生産性が自動化されていく。
情報管理
一人で全てを抱え込むのではなく、チームや外部のリソースをうまく活用する。コラボレーションで役割を分担し、ノート術やナレッジマネジメントで情報を整理する。AIやアウトソースを取り入れれば、自分の時間をより創造的な活動に振り向けられる。
- コラボレーション
- 情報整理(ノート、ナレッジマネジメント)
- 外部リソース活用
コラボレーション(チームでの情報共有、役割分担)
一人で全てを抱えるより、他者と協力した方が速くて強い。情報を共有し、役割を分担することで、チーム全体の生産性が最大化される。
情報整理術(ノート術、ナレッジマネジメント)
情報が散らばると再利用が難しい。ノート術やナレッジマネジメントを使って情報を体系化すれば、知識は資産となり、必要なときにすぐ活用できる。
外部リソースの活用(アウトソース、AIやツールの利用)
すべてを自力でやる必要はない。アウトソースやAIを活用することで、自分の時間を最も価値のある領域に集中させられる。